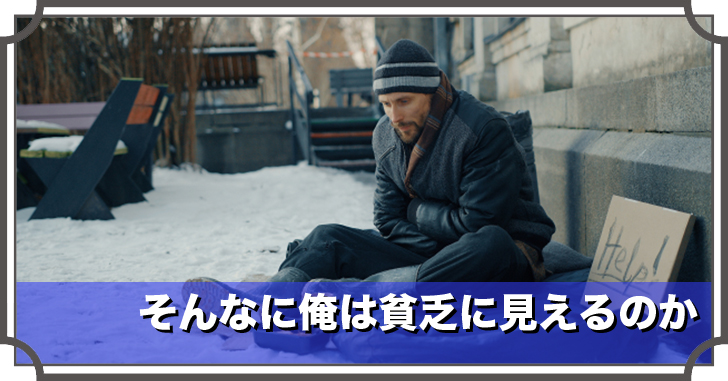昨夜はなかなか寝付かれず。
今頃になって眠くて眠くて…。
こんにちは。
シェービングサロン -Yesim- イエシム 事業主です。
ちょっとした調べ物をしている途中、面白い法律を見つけたので紹介します。
女子断髪禁止令
簡単に言えば、
「女性は髪を短く切ってはならない」
というものなのですが…。
えっ…
と思わせるこの法律、制定されたのは明治5年(1872年)。
今から100年以上も昔の話です。
公布したのは東京府(現在の東京都)とのことなので、これは法律というよりは現在で言うところの条例とか規則にあたるものですかね?
なぜこんな法が発布されたのかというと…
きっかけになったのは前年に公布された、とある法律。
明治4年(1871年)に制定された、
散髪脱刀令
俗に言う
断髪令
というものです。
それまで、髪型は髷(マゲ:ちょんまげの事)を結い、華族・士族は腰に刀を差していたものが、
「散髪、制服、略服、礼服ノ外、脱刀モ自今勝手タルベシ」
とのお触れを、政府が出したんですね。
要は、
「髪型や服装は自由にしても良いし、刀を腰に刺さなくても良い」
ということ。
それ以前は、身分ごとに髪型や服装が定められていたんですね。
これね、ちょっと勘違いしている人も多いようですが、
「髪型を自由にしていいよ」
っていうことであって、
「髷を落としなさい」
と、強制するものではないんですよね。
それまでの日本は、鎖国政策を取っていたというのは、歴史の授業で習ったとおりです。
で、1853年にペリーが来航し、すったもんだがあって…その後、開国に至るわけですが、蘇澳なると欧米諸国の人々との交流が一気に加速するわけです。
政府の命を受け、欧米諸国に視察に行った要人たちも、発達した近代文化や産業に驚き、
「このままでは我が日本は欧米諸国に遅れを取ってしまう。
一刻も早く欧米諸国に追いつき、肩を並べられるようにならなければいかん。」
と感じたようで。
で、そんな中…
日本人のちょんまげヘアーは、欧米人の目には非常に異質に映るわけです。
「おい、俺たち、変な目で見られてねぇか?」
ってことになり、視察に出発する時はちょんまげだった彼ら、シカゴで散髪したそうで、帰ってきたときにはすっかりザンギリ頭になっていたそうな。
そんな経緯から、欧米の文化をいち早く大衆に根付かせるため、この散髪脱刀令(断髪令)が施行されたのだとか。
でね…
そもそも「ちょんまげを切ってもいいですよ」っていう事なので、施行対象は男性に向けてのものだったのですが、断髪令施行後、髪を短く切る女性が続出。
なぜなら、
手入れが楽だから。
当時の日本女性の髪型は、いわゆる「日本髪」ってやつ。
鬢付け油(松やにと胡麻油の蝋に香料を混ぜたもの)をたっぷり使ってアップにした髪は、洗い落とすのに半日もかかると言われるほど手間がかかったそうで。
で、断髪令出たことだし、いっそのこと切ってしまえ!
となるのも、わからんでもないのですが…
女性の短髪姿に対して、世論が猛反発。
「長い黒髪こそ女性らしい姿」という価値観が浸透していたことに加え、男性のようなザンギリの断髪姿は娼婦を連想させるというらしいのです。
なぜザンギリ髪が娼婦を連想させるのかというと、江戸時代の身分制度では、賤民層(最下層)である非人の女子は日本髪を結っていなかったからというもので、現在で言うポニーテールやボブのような髪型だったそう。
で、そのような髪型で門付芸(もの乞い芸人)や売春を行っていたことから、髪を短くした女性はそのように見られてしまったんですね。
で、これらの世論の声に乗じて、
「女性の散髪は、まかりならん!」
とのお触れを出してしまったんですね。
さてさて、冒頭にも書きましたが、明治5年に施行されたこのお触れ、その後どうなったのかということが、どこを調べてもわかりません。
まさか、現在でも効力があるとは思えないのですが。
仮に法に反した場合の罰則等も不明なんですよね。
あ、そうそう、これも冒頭に述べましたが、東京府(現在の東京都)で施行された決まりなので、我が神奈川県では大丈夫です。
とりあえず東京都にお住いの女性の方、ショートヘアーにはご注意くださいませ。